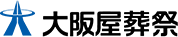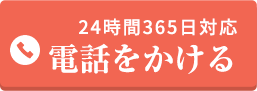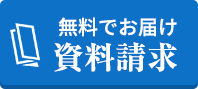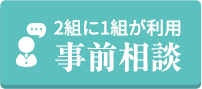今回の豆知識では納骨についての基本をご紹介させていただきます。
一周忌までには納骨を済ませる
納骨(埋葬)の時期に特に決まりはありませんが、一般的に仏式では、四十九日の法要に合わせて行うことが多いようです。
墓がない場合、一周忌をめやすに墓を用意して納骨します。
僧侶に依頼し「納骨式」を行う
四十九日法要の日に納骨を行う場合は、法要後、墓地に出向いて納骨式を行い、そのあとに会食の席を設けるのが一般的です。別の日に行うときは、僧侶と相談して日程を決めます。近親者を招き、式のあとに食事の席を設けます。
納骨の日程が決まり次第、事前に墓地の管理者に連絡をします。火葬許可書が必要になる場合があります。確認しておきましょう。
また、墓石か墓誌への戒名などの彫刻がある場合は、石材店に依頼の連絡をしておきます。
浄土真宗以外では、納骨式当日、施主や参列者が供養に卒塔婆を立てるしきたりがあります。複数本立てる場合もあります。式の1週間ほど前までに寺院に依頼しておきましょう。
遺族は喪服を着用します。遺骨、遺影、位牌とともに「埋葬許可書」と認め印を忘れずに持参しましょう。遺骨は、故人と最も血縁の深い人が運びます。
近年では近親者だけで「納骨式」を行うことも
先日、東龍寺墓地大阪屋樹木葬常滑北では、僧侶を呼ばす、親子3代、近親者だけの和やかな空気で「納骨式」を行っていただきました。
近年ではライフスタイルの変化から葬儀、お墓、納骨も様々な形で行われております。


散骨を希望するときは?
遺骨を墓地以外に埋葬することは法にふれます。「葬送のため節度を持って行えば違法ではない」とされていますが、自治体の中には散骨や散骨場の経営を禁止する条例を制定したところもあります。散骨では、遺骨をすべてまくケースもあれば、大部分は墓に納めて一部をまくケースもあります。すべてをまく場合は、その後の供養をどうするかなども考えておきましょう。
散骨は主に海洋や山中で行われます。陸地で行う場合は近隣とのトラブルになるといったこともよく耳にしますので注意が必要です。
近年注目されている樹木葬
近年は、墓地として許可を得た場所に遺骨を埋めて樹木を墓標とする「樹木葬」が注目されています。
大阪屋東龍寺墓地樹木葬常滑北では、おかげさまで、残り区画わずかとなっています。樹木葬に興味がある方は是非、お早めにご検討くださいませ。(※令和6年7月現在)
随時、現地の見学、相談を行っております。ご予約はお電話0569-35-4949、またはHPからお願いいたします。