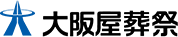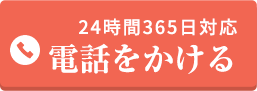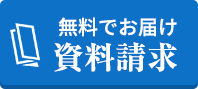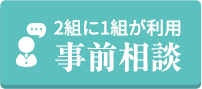枕飾りや葬儀で用いられるシキビ・樒(しきみ)は、別名「仏前草」と呼ばれ、古くから仏前に供える木として知られています。透明感のある淡黄色の花を咲かせ、実を結びますが、全体に毒性があり特に果実には強い毒が含まれています。そのため「悪しき実」と呼ばれ、それが略されて「シキミ」(シキビ)という名になったともいわれています。
香りと由来
「抹香臭い」という表現は、この木独特の香りに由来します。
毒性や香りの強さから、古来より「死者を悪霊から守る」「邪気を払う」と信じられてきました。また、その香りを獣が嫌うため、土葬の時代には遺体を獣から守る目的で墓地に植えられたり供えられたりする習慣もありました。
守りと浄めの意味
葬儀においては、シキビ(樒)を枕飾りや門樒として供えることで結界を張り、亡き人を邪気から守る意味があります。近親者が供花や供物の代わりに門樒や樒塔を供えることも一般的です。
お線香と同じように、シキビ(樒)の香りはその場を浄める効果があるとされ、古くから大切に受け継がれてきました。
虫よけ効果
シキビ(樒)には「サフロール」という成分が含まれており、虫よけの効果があります。ノミやダニの忌避剤にも用いられている成分で、お墓参りの際に樒を供えることで、お墓を虫から守る役割も果たします。
虫よけとしての実用性と、場を清める象徴性を兼ね備えている点も、シキビ(樒)が選ばれてきた理由の一つです。
樒と葬儀の関わり
樒は香木の代わりに抹香や線香の材料としても用いられています。その香りは場を清浄にし、亡くなった方を守ると信じられてきました。
葬儀で樒塔を供えることには、故人を偲ぶと同時に、その霊を守り導くという意味が込められています。

まとめ
シキビ(樒)は単なる葬儀の飾りではなく、古来より「守り」と「浄め」の役割を担ってきた大切な植物です。香りによる邪気払い、虫よけ効果、そして供養の象徴として、シキビ(樒)を供えることには深い意味があります。
常滑市での葬儀においても、この伝統を理解し、大切な方を守る想いを込めて樒塔を供えていただければ幸いです。